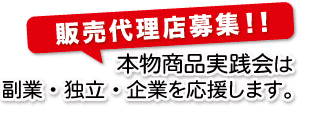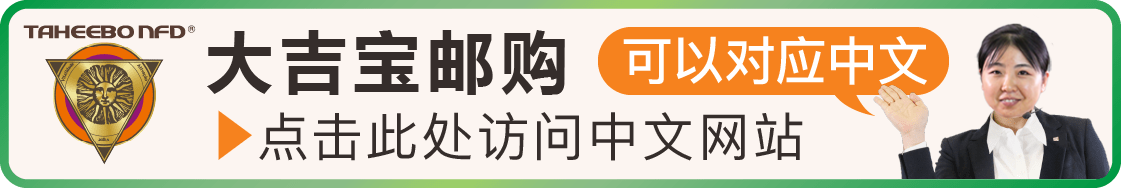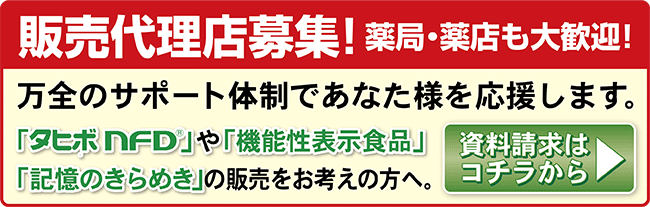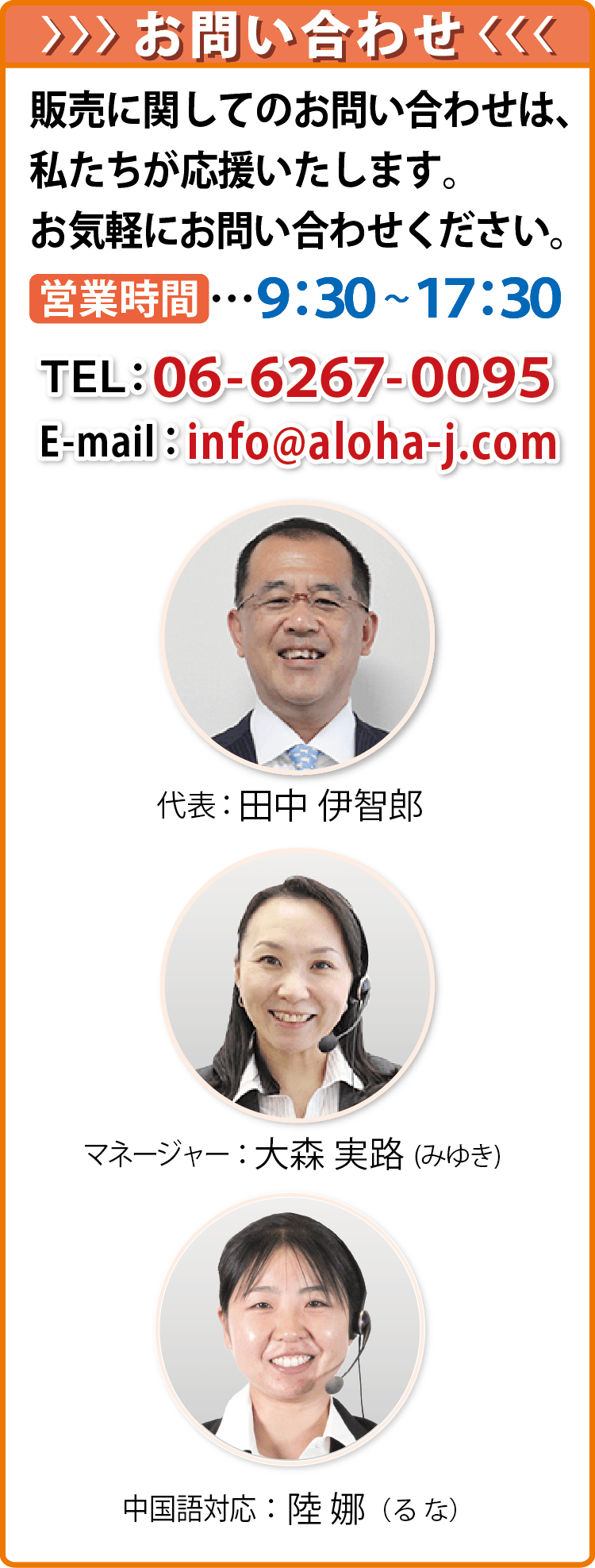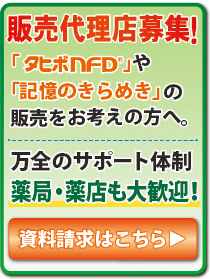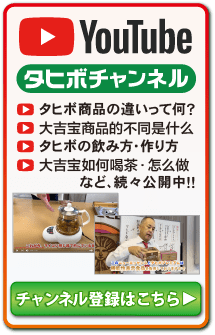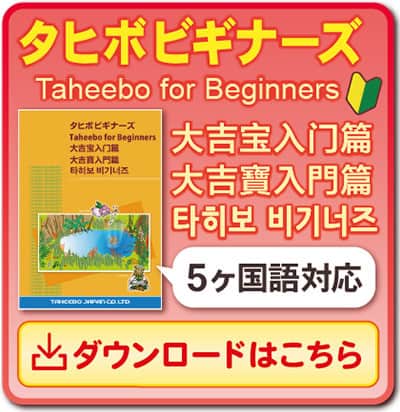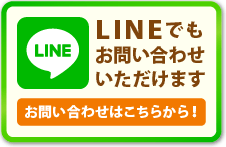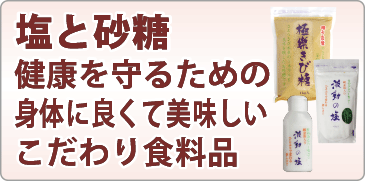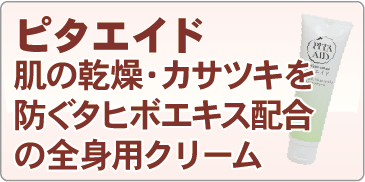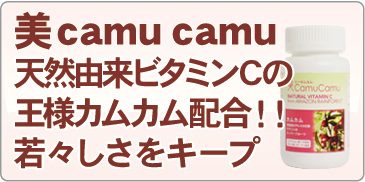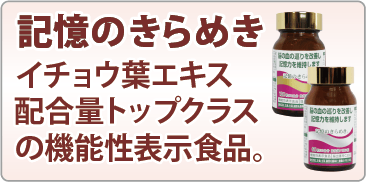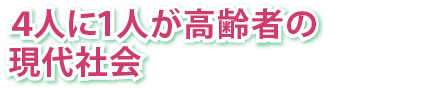
年齢を重ねるにつれ日々の生活の中で、「何だったかを思い出せない」「約束を忘れてしまった」などなど記憶力の低下を感じる高齢者は少なくありません。


「4人に1人が高齢者」という日本の高齢化社会、2035年には「3人に1人が高齢者」になるという推計も出され「超高齢化社会」を迎えると言われており、こうした悩みもより深刻になっていきます。

イチョウ葉栽培農園
アロハージャパンの「記憶のきらめき」は、スイスのリネア社(Linnea社)の素材を採用しています。リネア社のイチョウ葉は、ヨーロッパ・アメリカのイチョウ葉農園にて栽培収穫しております。乾燥〜最終製品化まですべての工程は「企業内」で一貫して品質管理するという適正農業規範“Good Agricultural Practice”(GAP)に従っております。
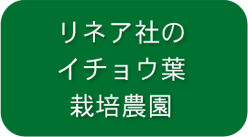

 農園では、殺虫剤を一切使用しない肥料のみのイチョウ葉栽培を行います。乾燥工程で袋詰めされたイチョウ葉はリネア社の自社倉庫で空調、温度管理を行い保管します。nまた出発原料は工程に入る前に必ず分析を行い、イチョウ葉は欧州薬局方(Eph.)モノグラフに準拠して分析を行います。
農園では、殺虫剤を一切使用しない肥料のみのイチョウ葉栽培を行います。乾燥工程で袋詰めされたイチョウ葉はリネア社の自社倉庫で空調、温度管理を行い保管します。nまた出発原料は工程に入る前に必ず分析を行い、イチョウ葉は欧州薬局方(Eph.)モノグラフに準拠して分析を行います。
「記憶のきらめき」は人体に有害なギンコール酸の残留量は5ppm以下を遵守しています。
最適な生産高を維持する為には気象、土壌などの管理栽培が重要となります。
・春先の気候が寒さの為、霜でイチョウの発芽が遅れたりしない温暖な気候
・夏の数ヶ月間、降雨が不十分であったりしない適正な雨量と土壌管理
・その年の気候によりイチョウ葉の育成状態が異ならない安定した気候と最適な生産高を維持する為の土壌管理
はイチョウ葉管理栽培には欠かせません。
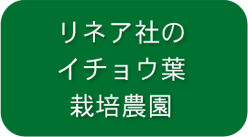


「記憶のきらめき」は人体に有害なギンコール酸の残留量は5ppm以下を遵守しています。
最適な生産高を維持する為には気象、土壌などの管理栽培が重要となります。
・春先の気候が寒さの為、霜でイチョウの発芽が遅れたりしない温暖な気候
・夏の数ヶ月間、降雨が不十分であったりしない適正な雨量と土壌管理
・その年の気候によりイチョウ葉の育成状態が異ならない安定した気候と最適な生産高を維持する為の土壌管理
はイチョウ葉管理栽培には欠かせません。
ヨーロッパ、アメリカで所有するイチョウ葉管理栽培農園では
・栽培用に特別仕様のトラクターを使用
・イチョウの木の成長を平均1.5mでイチョウ葉を栽培
・イチョウ葉に最も栄養が行き届く状態で収穫する為の状態維持
に努めております。
・栽培用に特別仕様のトラクターを使用
・イチョウの木の成長を平均1.5mでイチョウ葉を栽培
・イチョウ葉に最も栄養が行き届く状態で収穫する為の状態維持
に努めております。